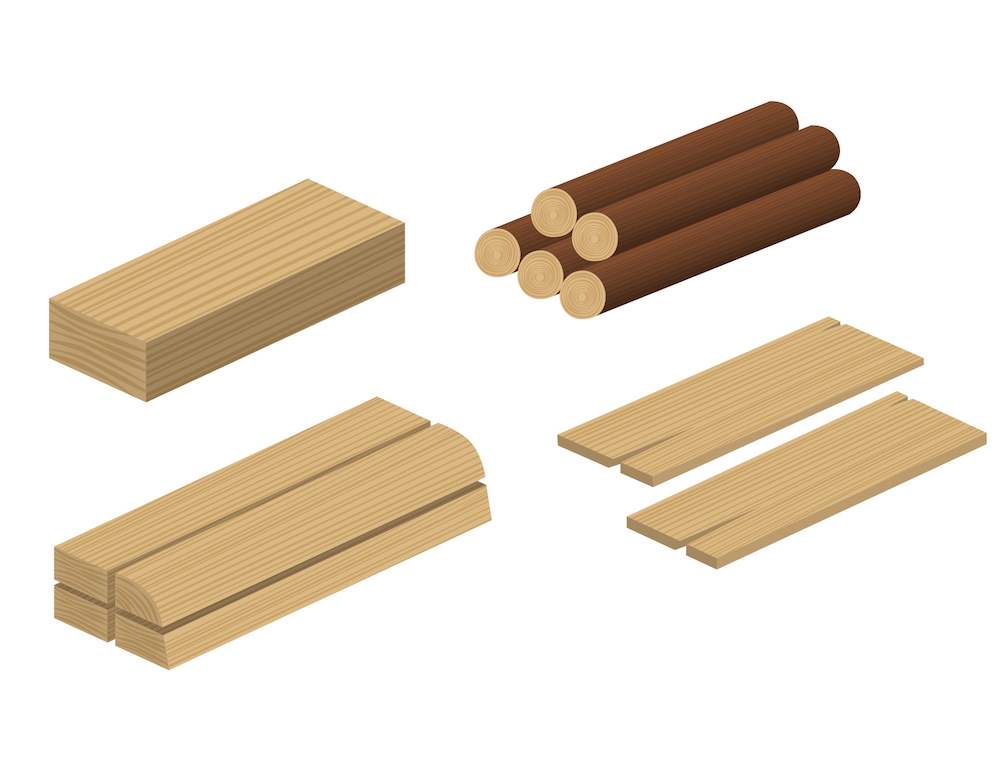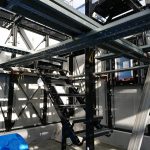工事現場における足場関係についてKRH社の解説
最終更新日 2025年6月18日
工事現場というと身近なところでは木造住宅等の工事現場がありますが、高さが13メートル、軒高9メートルを超える建物、木造以外2階以上の高さを持つものに対しては、地盤面から少なくとも1.8メートル以上の仮囲いを設けなければならないことが法律で決められているものです。
これは工事現場と外部との交通的な遮断や、盗難防止などの安全面、事故防止などの面で役立てられています。
建設会社の作業員やとび職と呼ばれる専門職が行う
そして足場工事は公共建築物や土木工事における構造物の建設、マンション建築などの高層建築物の工事などにも利用されております。
強度的なところから超高層建築物においてはタワークレーンなどの機械を用いて行われることになりますが、大抵は建設会社の作業員やとび職と呼ばれる専門職がこれを行うことになっています。
隣国では以前から高層建築物の足場さえ竹を利用することがニュースなどでも伝えられていましたが、鋼材で作られた部材が不足しているためにやむを得ず行われていたと想像できますが、安全面で見ると非常に危険な方法と捉えることもできるものです。
木造以外の構造の一定規模以上の現場ではまず、建設地の周囲に鋼製の仮囲いが設けられてから工事が始まるとされています。
仮設事務所とかトイレなどが設置され、建設建物などの周囲にはあらかじめ仮設工事の計画によって垂直方向に足場が組まれて行くことになります。
一定規模の工事では枠組み足場が組まれる
出入口や材料の搬入を行う昇降機の取り付け場所が決められ、一定規模の工事では枠組み足場が組まれて行きます。
出入口の幅が広いところでは鉄骨製のマグサが設置されることもあります。
まず地盤面は凹凸のないように均され、レベル調整がまず行われ、敷板を建物に平行に敷いてこの上にジャッキベースを載せて、建枠と呼ばれる幅600、900、1200ミリ幅のものを組み上げて行きます。
昇降階段や筋交い、足場板、手すりなども設置し、ジョイントやクランプという金具も使われます。
各職種の人の転落防止や防音、粉塵の飛散防止、風雨による揺れ防止の為に安全ネットや安全シートも外周に貼られ、壁つなぎと呼ばれる金物で建物と緊結され固定されます。
鉄骨構造の建物や構造物の場合には鉄骨の梁から吊りチェーンを吊り下げて角パイプ製の吊り桁、根太、安全ネットなどで作業できるように足元を整えます。
屋根に届くだけの丸太を組み上げることも多い
外回りの作業や移動にはこれらの場所が使われ、室内に移動できるようになると、天井工事とか壁工事を行うにはローリングタワーと呼ばれる移動が可能なキャスター付きのものが使われたり、脚立と呼ばれる簡易な装置が使われることも多いものです。
比較的に規模の小さい工事では屋根に届くだけの丸太を組み上げることも多いものですが、材料も不足し、安全面でも問題になることがあるためか次第に鋼製の材料に移行して来ているようです。
丸太を使う場合は、3メートルから8メートルぐらいの長さの丸太をなまし番線と呼ばれるもので交差する部分を締めあげて固定するものです。
狭い敷地などで工事を行う場合には地方では現在でも活用されているケースも見られます。
鋼管を使ったものでは単管で直径48.6ミリの鉄パイプを縦横に組み合わるものがよく知られています。
クランプ金具と呼ばれるものが使われ、職方の人も作業がしやすく、組める自由度も高いとされています。
くさび足場と呼ばれる方法について
KRHなどに代表されるくさび足場と呼ばれる方法も知られていて、これは緊結部分にクサビ方式を用いて組み立てるもので、建物の外壁にそって2列建地を組む方法で、1列組む場合はその専用のものもあるようです。
構造が簡単で軽量で、低層や中層の建物ではハンマーで打ち込むだけでできるので、低コストかつ時間短縮が可能なのでメリットも多く、工場とか倉庫では多く利用されこれまでにも実績を多く持っています。
作業を行う職方はトビと呼ばれ、作業ズボンも下部が広がり、足首の辺りで絞った独特のスタイルが見られ、トビ職と判断できます。
この職業は高所で作業を行い、ロープで下から建枠を引き上げたり、鋼製の板や階段を持ち上げたりするので体力を要し、かつ敏捷性が要求されるので、高所恐怖症の人には向かないかもしれません。
また、気象条件によって安全確認を行ったり補強作業を行う必要に迫られることもあったりするので、サラリーマン勤務のような生活にはならないことが想像できます。
歴史的に過去を振り返ると丸太部材は1950年代に森林保護の観点から鋼管製のものに移行して行ったとされ、しかも長く使ううちに朽ちてきて強度も保証できなくなり、折れたりすると人身事故にも結び付くことがあったりして次第に使われなくなって行ったと考えられています。
鉄パイプが組み合わされた単管を使ったものが最初に使用されたのは東京都の大手町の作業現場とされていいます。
同時期に枠組みのものが登場することになりますが、コストが高いところからなかなか普及が進まず、主に造船所や一部の土木工事の作業現場で使われているに過ぎなかったと言われています。
その間の経済成長や1979年にクサビ式のものがハンマー1本あれば組み立て可能なところから、相当に普及して行ったと見做されています。